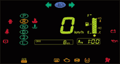
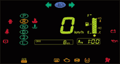 |
秘密のエンジンルームのぺーじ |
 |
タイヤチェーン着装訓練! |
 |
 |
| 今回は新しく買ったチェーン?のインプレッション・・・というつもりでしたが、この暖冬で東京はおろか正月に行った白樺湖でも夏タイヤで十分な道路状況でしたので、仕方なくインプレッションというより着装のポイントなどを紹介したいと思います。 もともとタイヤチェーンは持っていましたが、オールシーズンタイヤ「ベクター3」と4駆の組み合わせで、東京の雪程度はチェーンの必要な状況はあまりありません。今は普通のタイヤですが、次回のタイヤ交換では新型のオールシーズン「ベクター5」にしようと考えていますので、それまでのつなぎということで、あまりコストをかける気もありませんでした。 |
|
 |
スーパークイックチェーンの場合 |
 |
 |
| まずは、安価で性能も高く、装着も簡単な一般的な金属チェーンを代表して(株)東邦トレーディング社の金属亀甲チェーン「スーパークイックチェーン」です。 こちら、特にどうということのない物ですが、他車の簡単装着チェーンも金具の形状や締め付け方法が違うだけで、基本的には同様なので参考にしてください。 ケースは樹脂製の平べったい物で、トランクの下に入れておくと、収納スペースを食いません。また、汚れた物を収納するのも、くるっとリングを捻って納めるだけなので、簡単です。 構造はタイヤの裏側回す太いワイヤーに緑色のカバーが被っていて、向きがわかりやすいように片側が黄色になっています。 クイックチェーンの特徴として路面に当たるチェーン部分も二つに分かれて、被せやすいようになっており、その留め方に各社特徴があります。 締め付けも細いチェーンになっていますが、こちらも黄色と赤に塗り分けられて、順番が判りやすい様になっています。 |
|
 |
 |
| 取付方法はまず、裏側に回すワイヤー部分をタイヤの下から通します。本当は赤い締め付けチェーンを右側に持ってくるときちんと被せるチェーンが左右に分かれてくれるようになっているのですが、写真はそれを忘れています・・・ また、ワイヤーの端部は六角形の金具を引っ掛けるだけなのですが、メス側は変形しやすく、私も外した時にタイヤで踏んづけて変形させてしまいましたので、離脱して車を移動する時には注意をしましょう。 |
|
 |
 |
| ワイヤーを金具で繋ぎ、チェーン部分を被せながらワイヤーの環を裏側に回します。 ワイヤー自体、非常に腰が強いので、裏側にドサッと落っこちてしまうことはありません。ただし、ここでチェーン部分をきちんとねじれない様に整理しながら被せていかないと、それ程長さに余裕がありません(=緩まないで掛けられる)ので、ここは慎重に作業しましょう。 |
|
 |
 |
| チェーン部分は黄色い端部を緑色のフックに掛けるということで外側も一体化します。 さらにもう一端は締め付けチェーンに繋がっていますので、赤いフックと赤いリングを通して、端を黄色チェーンに引っ掛ければ取付完了です。 もちろん、一定距離を走行して締め直すというのは、自動的に締まっていくタイプ以外どんなチェーンでも基本ですのでお忘れなく。 このチェーンも普通のはしご型チェーンとは違い、亀甲型ですので横滑りにも強く、走破性には問題ありませんが、走行時の振動、特に舗装が露出している場合には厳しいのは仕方ありません。 |
|
 |
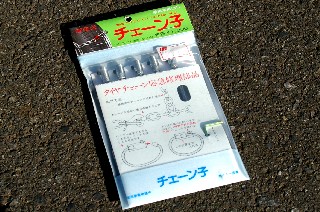 |
| さて、金属チェーンも取付方が悪かったり、舗装が露出している状態で長距離走行していると、チェーンが切れて、最悪その端部がボデーやサスペンション、ブレーキホースなどを損傷させる恐れがあります。 写真左はたまたま黄色いチェーンが一回くぐってしまって捩れが生じている状態です。このような状態で走行すると、切断の危険が高くなります。 そこで、金属チェーンに入れておきたいのが、このようなチェーン補修用のキットです。写真はワイヤーを六角レンチで取り付けるタイプですが、チェーンのコマをペンチで締め付けるものなどがありますが、太目の針金(できればビニール被覆の物)でも代用が可能です。 |
|
 |
最近話題の新チェーン? オートソック! |
 |
 |
| 次は、今回新たに購入したニューアイテム「オートソック」です。 最近ネットだけでなく、特にホイールクリアランスの少ないホンダ車だけでなく、トヨタ車でもディーラーOPに設定されるようになり、ご存知の方も多いと思います。 物としては非常にコンパクト。ビニールバックに4つ折にした本体と、ビニール手袋、取説が入っており、金属部分は全くありませんので、常にトランクといわず、シートポケットに放り込んでおいても邪魔になりません。 材質は合成繊維のネットにバンド、トレッド面は土のう袋に使われているような繊維です。 発想としては、スタックした時にタイヤの下に古毛布を敷いて脱出しようというものですが、性能的には状況によってスタッドレスを上回る性能を発揮する場合もあるようで、氷面の水分を繊維で切り離すと共に、毛糸の手袋に雪が引っ付くあの現象を利用しているためで、かなりの走破性を発揮すると共に、全くのフラットな設置面なので、快適な乗り心地を確保できます。 |
|
 |
 |
| オートソックは構造的には巨大なシャワーキャップのようなもので、裏側に回す部分には協力はゴムバンドでしめるようになっています。 ですから取り付ける場合は、とりあえずグッとゴムを広げてタイヤの上側に被せ、上半分に広げます。 この時、できるだけきれいにトレッド面を合わせた方が後ほどうまくいくようです。 |
|
 |
 |
| 上半分を被せたら、一般のチェーン取り付け要領のように、車をタイヤ半回転分動かして反対側も被せ、形を整えて装着完了です。なんの工夫もいりませんし、うちの車のようにホイールハウスが広ければ手も汚れないと思います。 右の写真のように、ちょっとトレッド面がずれていても、走行することで中心が合ってくるので問題はないとのことですが、インプレによるとネット面はあまり強くないようなので、小さめのタイヤサイズの場合は余りが生じないよう本格走行の前に調整しておいた方がいいようです。 |
|
 |
 |
| 取り外す際にはオレンジのバンドを引っ張って(当然上側)外し、タイヤを半回転させれば完了です。 注意しなければならないのは、雪の面にそのまま置いておくと、くっついて取れなくなってしまいますので、すぐに収容することです。 さて問題の耐久性なのですが、雪道のみで150キロ、舗装が露出していると50キロ程度と言われています。走破性は文句なしですが、やはり応急用であることには間違いありません。この付け外しの簡単さは、都内のように駐車場の敷地内や路地は凍結していて、幹線道路まで出られればいいというような場合に向いているのかもしれません。 洗濯もできますので、大事に使えば元は取れるのではないかと思います。 性能のインプレについては、来年になるかもしれませんが・・・ |
|