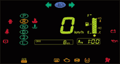 |
スパシオなぺーじ |
| 「山形・銀山温泉と宮城県・松島に行ってきました!」 |
 |
 |
| 今回は震災後初の東北遠征、久しぶり一千キロ級のドライブレポートです。 正直、「高齢者を目的地に送る」というのが今回の目的で、特に観光が目的ではないことから、いつも以上に脈絡のない旅行記なることを御了承頂きたいと思います。 |
 |
|
| 最初の目的地は山形県鶴岡市です。東京・多摩地区から東北地方に向かうには首都高速経由か圏央道経由で東北道に入るルートが一般的ですが、圏央道も一部未開通部分は一般道通行となることから、今回は20キロ程距離が短く、景色も変化の多い関越道新潟経由のルートを取りました。 この日は金曜日なのですが、休みを取ったはずの会社から電話が入り、30分程足止めを食っただけで、渋滞もなく快適なドライブスタートです。 |
 |
 |
| このコースでは関越道から北陸道北進、日本海東北道と渡りますが、もうこの先には昼食を取れるサービスエリアがありませんので、最後の越後川口SAで昼食を摂りました。 こちらの名物は米粉を使った麺類ですが、私はがっつり系の名物「新潟妻有ポーク丼」を頂きました。予想外の辛めソース味タレでインパクト十分です。デザートにはにんじんゼリーが付きます。 |
|
 |
 |
| 関越自動車道から長岡Jct.で北陸自動車道へ、さらに新潟中央Jct.で日本海東北自動車道に渡ります。 日本海東北自動車道は荒川胎内ICから日本海沿岸東北自動車道となり無料区間になり、新潟県村上市内の朝日まほろばICで現供用区間は終了します。 ここからは国道7号線、通称羽州浜街道を鶴岡市市街まで進みますが、この区間は半分は海沿いの快適なドライブが楽しめます。 |
|
 |
 |
| 鶴岡市及び酒田市での用事を済ませ、日も落ちかけてきた時刻になって、この日の宿泊地である銀山温泉に向かいます。 距離にして夜久90キロ、一般道でナビでも2時間以上と出ていたため、宿に遅れそうだとの連絡をしたところ、「1時間半も掛かりませんよ。」との回答が…?ルートは国道47号線(南野バイパス・鶴岡街道)から国道13号線(尾花沢新庄道路)を進みます。 R47が国道345号線に差し掛かる辺りになると、前方に多くの風車群が見えてきます。こちらは旧立川町(現在は庄内町)が風にこだわった町おこしのために1992年から始まった風車村計画「ウインドファーム立川」です。1995年には町おこし的発想から本格的な風力発電に切り替わり、町全体の消費電力量約2,200万kWhを風力発電を中心とした新エネルギーで賄おうという壮大な計画になっています。現在は11基の風車が稼動し、年間約1,267万kWhが発電でき町内で消費される電力の約57%を賄う規模になっています。 |
|
 |
 |
| ウインドファームの先は最上川と陸羽西線(通称:奥の細道最上川ライン)沿いに走ります。道幅は広くありませんが相当な速度で流れており、交差点も少なく、美しい風景と適当な山坂道で快適なドライブルートです。 | |
 |
 |
| R47は新庄市で尾花沢新庄道路という自動車専用道路に接続します。 この道路、無料の自動車専用道ですが、実質的には制限速度70キロの対面高速道路で、一気に時間の短縮が図れます。確かにここを流れに乗せて走れば、銀山温泉まで1時間半も無理はありません。 |
|
 |
 |
 |
尾花沢新庄道路の供用部分を終点まで行き、国道347号線母袋街道に進みます。 この道はこの付近の山形から宮城に抜ける数少ない街道なので、交通量は少ないですが結構立派な道です。薄暮時に直線区間を山に向かって走っていると、未知との遭遇状態です。 しばらく進むと集落沿いに進みますが、銀山温泉方面に曲がると、すっかり田舎道ですが、十分な広さの立派な道です。外灯も人通りもほとんどありません。 |
 |
 |
| さらに進むと本日宿泊の宿「瀧見舘」への分岐と案内看板が見られます。 銀山温泉街への車の進入はできませんので、車両はこの付近やこの先の共用駐車場までとなりますが、瀧見舘へは右の道を進めば、少々細くて見通しが悪い道ですがで宿のそばまで行くことができます。 |
|
 |
 |
| 瀧見舘は銀山温泉街から少し離れた山の中腹にあり、古い風情の銀山温泉においては新しい造りの旅館です。階層は地下(といっても谷の中腹の浴場)から2階までですがエレベーターもあり、高齢者にも安心です。 | |
 |
 |
| 館内のパッケージ型消火設備のボックスデザインは、内装に合わせてこんなタイプが。 これは製品で、オリジナルデザインではありませんが、マッチしています。 |
 |
 |
| 客室もきれいに整備されていて、十分な広さです。浴室はありませんが洗面台は2面あり、うがい薬が準備されているなど、こまかい気配りがされています。 | |
 |
 |
| そして、お楽しみの夕食ですが、1階の食事処の個室で頂きます。 内容は地の物中心で、ひとつひとつに調理長の仕事が生かされていて個性、内容、味ともに満足できました。特に出汁については、すき焼きや茶碗蒸しはやさしい出汁なのに対し、山菜汁は身欠きにしんの強い出汁、そばつゆは江戸前風の辛い出汁と、よく考えられています。この宿は「滝と蕎麦の宿」とうたい、十割の極太で腰の強い蕎麦が名物で、非常にインパクトのあるおいしい蕎麦でした。 残念だったのは中居さんの対応で、料理のことを何も分かっていなかったことと、蕎麦のおかわりが時間切れでできなくなるのを事前に説明しなかったこと。ホントに残念な対応です。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 食前酒:山ぶどう酒 座付:ふきのとう煮浸し、凍み大根、鯉子煮、笹巻き、いたどり油炒め、細竹味噌煮、蟹松風、うぐい甘露煮 差し味:鮪、鱸、北寄貝、サーモン、ボタン海老 凌ぎ:手打ち蕎麦 肉料理:山形牛スキヤキ風牛鍋 焼物:天然鯛パリパリ焼き 蒸し物:淡々茶碗蒸し 口替り:中華風冷奴油淋ソース 香の物:尾花沢漬盛り合わせ 汁:山菜汁 食事:こしあぶら御飯 デザート:柚子シャーベット | ||
 |
そして朝食も御覧のとおり豪華な内容で、実はパン食とのチョイス、魚のチョイス、副菜の追加もできる細かな気遣いがあります。 料理については満点です。 |
 |
 |
| さて、銀山温泉街には、伊香保や草津、鬼怒川といったところにあるような温泉街のアミューズメントがあるわけではありませんが、雪の風景とガス灯に映し出される夜景は、小さい温泉ながらも散策を楽しませてくれます。 夜景散策も、お土産屋さんや飲食店も早仕舞いなので、純粋に温泉街の風景を大切な人と二人で楽しんでください。そういったスポットです。 |
|
 |
 |
| 銀山温泉は御存知のとおり、大正期の高層木造旅館の風情の残る温泉街として有名ですが、その多くは外観やイメージのみ残して大きく改装されしまっています。その中で内外ともに昔の「旅籠」の風情が残っているのが、創業が明治2年、現在の建物が大正2年造の旅館「小関館」です。 残念ながら現在は日帰り入浴と休憩のみの営業のようですが、襖のみで仕切られた客室などが最後まで残されているとのことです。 |
|
 |
 |
| 銀山温泉のイメージリーダーであり、一番の威風を放っているのが「能登屋旅館」です。 創業は明治27年、現在の建物は大正10年造とのことで、鐘楼の付いた道後温泉本館にも劣らないこの建物は、銀山温泉で唯一国の登録文化財に指定されています。 玄関から除いてみると極めて近代的な旅館に生まれ変わっており、エレベーターも付いています。一方で建物の正面右側には、左官職人の後藤市蔵が昭和7年に作製した、銀山開拓の祖である「木戸佐左ェ門」の名が記されてい鏝絵が残されています。 |
|
 |
 |
| 創業は江戸中期という老舗旅館の「古山閣」。こちらの特徴は、正面の2階部分に並べられた鏝絵の立派さです。 日本の年中行事を連ねた色鮮やかな鏝絵は、近代的に改装された旅館の丁度と対峙しています。 |
|
 |
 |
| さて、瀧見舘は温泉街の上の山の中腹にありますが、温泉街へは10分も掛からずに降りていくことができます。下りた先に見えるのは銀山川の上流側で轟音を立てているのが、落差22mの白銀の滝です。 昼に上空から見る銀山温泉街は、谷間の小さな集落に見えますね。 ちなみに、温泉街に下りていったところに「蕎麦処滝見館」があり、宿で食べた蕎麦がこちらでも頂けます。 |
|
 |
 |
| 白銀の滝の上流側は人骨を思わせるような少し赤み掛かった岩が露出する渓谷「洗心峡」があります。 白々しい程の美しい緩やかな屈曲を見せる川は新緑の美しさはもちろんですが、紅葉時期には信じられないような美しい風景になることでしょう。 川床の岩には川の流れと石の作用で削られてできる「ポットホール」が多数見られました。 |
|
 |
 |
| 温泉街から銀山跡(銀鉱洞)への散策路の途中にあるのが「河鹿橋」です。 実は今回、近代建築・土木遺産マニアの私としては、銀山温泉の夜景と並んでコレを見るのが楽しみだったんです。この橋は昭和10年製と、うちのお袋と同い年でした。 |
|
 |
 |
| 美しい赤み掛かったアーチ橋で、てっきりレンガか石橋と思いきや、コンクリート造のようです。 さすがに橋の路面は大分風化して骨材が露出していますが、よく見てみると砕石に混じって貝殻のようなものが入っているのが分かります。 |
|
| そして、松島へ・・・ |
 |
 |
| 銀山温泉を離れ、一路宮城県の松島に向かいます。 この付近から宮城県方面に抜ける道は少なく、この国道347号線、通称母袋街道で鍋越峠を越えるのが常道です。 母袋街道は決して広い道ではありませんが、走りやすい快適な山坂道です。国境を越えると中羽前街道を名前が変わり、若干道路幅が狭くなります。所々1.5車線位の幅の部分もありますが、地元の車は思い切り膨らんで飛ばして来ますので、通行には注意が必要です。 |
|
 |
|
| 途中、トイレ休憩で寄ったのが黒川郡大郷町にある「道の駅おおさと」です。まあ、正直これといった特徴のない道の駅ですが、名物はモロヘイヤ製品と姉妹駅「沖縄・許田」の沖縄グッズ、それとなぜかネパール人が持ち込んでいるというネパールグッズ?? 食事処があるのもウリです。 |
 |
 |
| この日の松島は生憎の雨でしたが、土曜日ということもあって道路も駐車場も結構な渋滞でした。松島の駐車場は中心部に大きな駐車場というところはありませんが、各所に点在しそれなりに空いているところもありますので、使う施設に合わせて利用するといいでしょう。今回は観光桟橋を出越した先のコインパーキング、松島プリンスパーキングを利用しました。 そしてこの日の昼食は、観光桟橋の正面にある複合飲食施設「丸山本店 松島玉手箱館」に入りました。 |
|
 |
 |
| 松島玉手箱館には1階がお土産名店街とカキカレーパンの石窯パン工房パンセなど、2階が寿司、海鮮丼、とんかつの表禅房おりこ乃、4階が牡蠣料理かき松島こうは、そして3階が今回利用した生そば、海鮮の松吟庵です。 まあ、各店フードコートのような気軽な店なので、この店もそばだけでなくていろいろなものが食べられます。松島のウリなのが牡蠣料理はもちろん、穴子丼も地域名物として推進しているとのことなので、牡蠣フライ膳と穴子丼を頂きました。結構おいしかったです。 |
|
 |
 |
| 松島の象徴的な建物で東北最古の桃山建築といわれているのが、「五大堂」です。 伝承によれば大同2年(807年)に坂上田村麻呂が奥州遠征の際に、この地に建立した毘沙門堂が始まりとされ、その後、円仁(慈覚大師)が瑞巌寺前身であるの延福寺を創建した際に仏堂を建立し、中央に大聖不動明王、東方に降三世明王、西方に大威徳明王、南方に軍荼利明王、そして北方に金剛夜叉明王の五大明王像を安置したことから五大堂と呼ばれるようになったとのことです。現在の堂は、慶長9年(1604年)に、伊達政宗が瑞巌寺の再興に先立って再建した建物です。 |
|
 |
 |
| 五大堂は島自体が聖域になっており、そこに渡る3つの橋はこのように足元から海面が見えるようになっていることから、「すかし橋」と呼ばれています。 すかし橋は江戸時代中頃の記録に既にこのような構造だったということで、聖域である五大堂への参詣には身も心も乱れのないように足元を良く照顧して気を引き締めさせるための配慮だといわれています。 |
|
 |
 |
| そして、松島観光といえば観光船による洋上からの観光です。 東日本大震災の津波被害について松島は他の地域よりは被害が少なかったものの、3m程の津波が押し寄せ、沿道の商店だけでなく観光船や浮桟橋も流出するなど、大きな被害を受けています。それでもこの地区の復興シンボルとして、流出した観光船を捜索して再整備し、4月末のGW直前には一部運行を再開しています。 前述のとおり松島観光自体見た目には多くの観光客が訪れており、瑞巌寺の平成の大修理(これは震災前から行われていた。)が完了すれば、一層の増加を期待したいものです。 |
|
 |
 |
| 今回乗船したのは、松島島巡り観光船の第三仁王丸、観光船の中でも総トン数188トン、定員407名と最大級を誇ります。竣工は平成11年、航海速力14ノットです。 この日は結構な混雑で、1階の一般席は窓側の席がほぼ埋まっていたので、600円の追加料金で2階のグリーン席に移動しました。 |
|
 |
 |
| 御存知のとおり松島は大小260の島々からなる地域ですが、元々第三紀層で構成された松島丘陵の凝灰岩、砂岩、礫岩など、侵食に非常に脆い岩質で出来ており、また、七ヶ浜半島と地続きであった浦戸諸島付近が869年(貞観11年)の貞観地震・津波によって沈水し島となったとも言われています。 今回の東日本大震災でこの地域に津波被害が少なかったのは、この島々が防波堤の役割をしたことと言われていますが、その分各島や岩への被害も少なからずありました。 また、松島湾名物の牡蠣養殖も一時全滅しましたが、他地域からの支援で往時の5割程度までは回復しているとのことでした。 左の写真は、松島奇岩の中でも代表的な「仁王島」、仁王様が煙管をくわえて座っている図にみえるとか。 右の写真は浦戸諸島最大の桂島、人口400人が住んでいます。母島や式根島って感じ? |
|
 |
 |
| さて、松島の観光船といえば、デッキからのカモメの餌付けですが、想像以上にカモメの数や群れ方がハンパありません。他の船が航行しているのを遠くに見ると、まるでカモメの大群に襲われているようにも見えます。写真のように従えて航行していると思ったら、すれ違った船に一斉に移動したりと、いろいろカモメも考えているようです。 今回の観光船のコースは17キロ約50分で湾を一周するコースで、一部外海に面した部分では若干の揺れがあります。また、航路によっては、塩釜への渡し舟コースもあります。 |
|
 |
 |
| 松島から仙台市内に向かいましたが、途中通った塩竈市内では道路端に打ち上げられたクルーザーが放置されていたり、閉鎖したり更地になっている商店なども目立ちました。 また仙台市内、特に駅前では、外壁に被害を受けたビルの修繕が多く行われているとのことでした。 |
|
 |
 |
| 最終日の昼食は、近過ぎて意外に寄らない、東北道栃木県の佐野SAで道中食べなかった佐野ラーメンを頂きました(写真は一番スタンダードな佐野玉子ちゃん)。やはりシンプルな出汁の醤油スープと平打ち縮れ麺はハマります。 当然のように御当地ラーメンをお土産に買って帰ったということは、言うまでもありません。 |
|