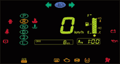 |
秘密のエンジンルームのぺーじ |
| 新デジカメ、PENTAX K-30を導入しました! |
 |
| 超久しぶりの更新になります。クルマ関係もいじるところなく、故障もなく、オフ会も旅行もなかった…つまりネタがなかっただけなのですが、そろそろ更新なのは電子デバイス関係でしょう。 ということで、今回は、ようやくデジタル一眼レフカメラを買い換えましたので、そのレポートです。 さて、PENTAXといえば、フィルムカメラ時代から先駆的な技術と小型軽量技術を駆使して光学機器分野で常に話題を作ってきましたが、どうしても後発する双璧のニコンとキヤノン製品に技術をパクられ、製品としてはいい物を作りながら「知る人ぞ知る」メーカーになってしまっています。 私は小学生の時に買ってもらった「KX」(1975年、バヨネット式Kマウントを採用した初代)以来PENTAXとの付き合いが続いており、超小型絞り優先AE機の「ME」(1976年)、コンパクトカメラで105㎜ズームや各種マニュアル操作機能を満載した「ZOOM105super」(1990年)、300万画素3倍ズームクラスデジカメとして世界最小・最軽量だった「Optio330」(2001年)、そして2006年製の「*istDL2」まで5代に渡り、この「K-30」で6代目になります。 PENTAXは、2006年のHOYAとの合併・経営統合、2011年のリコーによるデジタルカメラ事業の買収と完全子会社化、そして2013年に社名からペンタックスの文字が消え、光学機器のブランド名としてのみ残る今、いつまで「PENTAX」のカメラを使い続けられるか、ペンタックスファミリーとしてはいつもヒヤヒヤしています。 |
| K-30とは? |
 |
|
| PENTAXのデジタル一眼レフカメラは、2003年の初代「*istD」以降、ハイエンド機とエントリー機を相次いでラインナップするのが定番で、ハイエンド機の系譜は*istDS(2004年)→*istDS2(2005年)→K10D(2006年)→K20D(2008年)→K-7(2009年)→K-5(2010年)→K-5Ⅱ(2012年)そして現在のフラッグシップモデルであるK-3(2013年)に至ります。 一方でエントリーモデルの方の系譜は、*istDL(2005年)→*istDL2(2006年)→K100D(2006年)→K100DSuper(2007年)→K200D(2008年)→K-m(2008年)→K-x(2009年)→K-r(2010年)→K-50(2013年)となっています。 「あれ、K-30の位置づけってどこ?」なのでしょうか?? 実はPENKAXの一眼デジカメ進化は、エントリー機が型落ちのハイエンド機の性能に肉薄して新登場し、その後ハイエンド機が一気に性能向上を図るといったモデルチェンジを繰り返しているのです。ところが、K-m以降、HOYA戦略なのかキヤノンEOSKissシリーズを意識してか、性能向上よりはカラーバリエーションなど女性・初心者確保路線となり、ハイエンド機との性能格差が広がってしまいました。 そこで、2年型落ちのK-5の性能に匹敵しながら、K-rのコンセプトを踏襲した中間モデルとして登場したのが「K-30」だったのです。 K-30は現在ライン落ちし、その位置付けはエントリーモデルのK-50に引き継がれていますが、カメラ的にはK-50はK-30のマイナーチェンジに過ぎず、性能差はほとんどないため、K-50の発売直後には価格差からK-30の爆発的な販売増に繋がり、なんと2013年8月には価格.comのデジタル一眼レフカメラの売れ筋ランキングで堂々の(PENTAX初の?)1位になったそうです。 私もK-50に手を出さなかったのはこのためで、K-30は39,800円(ボデーのみ)で購入できました。今の方がかえって上がっているみたいですね? |
 |
 |
| いきなりですが、K-30最大の欠点といわれているのが、このペンタプリズム部のデザインです。PENTAXの歴代デジカメには見られない直線的なデザインで、昔のフィルムカメラ時代を彷彿とさせます(しかもオリンパスやミノルタ?)。 このでこっぱち・リーゼントデザインがあまりにも不評だったので、K-50が早々に出たとの都市伝説まであるくらいです。 まぁ、このらしくないデザインがあって、一般ユーザーに受け入れられたという声もありますが、私はあまりデザインはどうでもいい方なので。 しかし、このデザインがなんで盛り込まれたのかというと…? |
|
 |
|
| これも一説ですが、内蔵ストロボの位置をできるだけ本体から離し、ケラレを防止するためだと考えられています。 ボデーサイズに比較すると、ホントに上の方に持ち上げられています。 ちなみに、内蔵ストロボのガイドナンバーは12(ISO 100/m)で、*istDL2が15.6(ISO 200/m)と比較すると高性能化しているってこと? |
 |
 |
| さて、画質など基本スペックは後述するとして、K-30が上位機種にそん色ない操作性を持った部分はこちら。*istDL2ではモードダイヤルを左側配置し、右側には情報モニタを配していましたが、K-30では情報モニタを廃し(メインモニタ部に表示)、モードダイヤルをオーソドックスな位置に戻しました。そしてこれまで上位機種にしかなかったTAv(シャッター&絞り優先自動露出)モードやグリップ部にも付けられたダブル電子ダイヤル、さらにP(プログラム)モードにしておけば、モードダイヤルを回すことなくシャッター・絞り変更や各モードAE切り替えのできる「ハイパープログラムモード」、と「ハイパーマニュアルモード」を搭載し、様々な撮影シーンに素早く対応できる仕様になりました。 メインモニタの情報画面は、ちょっと慣れないと見づらい感じはします(普段はうっとおしいので消していますので。)。 ちなみに、JPEG16Mで4GBメモリーカード使用だと、撮影可能枚数は422枚となります。 |
|
 |
|
| ファインダー内の表示はこんな感じ。*istDL2に無かったのは、ISOがコントローラブルになった関係でISO表示が加わったのと、電子水準器(中央の目盛)が表示できるようになっています。 表示内容はモード切替や設定変更でかなりいじれるようになっています。 また、本機ではペンタックス独自の手ぶれ補正機構SR(Shake Reduction)により、望遠撮影や夜間撮影時の手ぶれ防止が図れます。 |
 |
|
| もう一つ、上位機のK-3やK-5にはないのが、「単三電池対応」バッテリーです。 K-30の場合は標準品として専用リチウムイオンバッテリー(左1050mAh)と専用充電器が同梱されています。この他に電池ホルダを使えば単三型電池が使用可能です。専用電池ですと480枚撮影可能ですが、エネループの場合、一本で1900mAhありますから、さらに撮影枚数が増えそうです。 ちなみに同等のバッテリーや乾電池ホルダはネット上に乱立していますので、純正品にこだわらない人は予備ならこれでも十分かも? なお、K-50には付属品として単三型リチウム電池(使い切り)しか同梱されていません。ということで、専用リチウム電池や充電器、充電式ニッケル水素電池など別に購入しなければなりませんので、純正品だけで揃えるとなると、場合によっては1万円近い出費を迫られる場合もありますので、注意が必要です。 |
| *IstDL2から、どの程度進化したのか? |
|
K-30 |
*ist DL2 | |
| 画素数 | 約1628万画素(有効画素) 約1649万画素(総画素 |
約610万画素(有効画素) |
| 撮影素子 | APS-C23.7 x 15.7 mm CMOS | APS-C23.5 x 15.7 mm CCD |
| 高感度(ISO感度) | ISO100-12800 | ISO200-3200 |
| 連写撮影 | 約6.0コマ/秒 | 約2.8コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/6000-30秒 | 1/4000-30秒 |
| 液晶モニター | 3インチ92.1万ドット | 2.5インチ21万ドット |
| ファインダー形式 | ペンタプリズム | ペンタミラー |
| ファインダー視野率 | 約100% | 約96% |
| ファインダー倍率 | 約0.92倍 | 約0.85倍 |
| 電池タイプ | D-LI109(単三使用可) | 単三 x 4 |
| 電池寿命(撮影枚数) | 約480枚 | 約850枚 |
| 記録メディア | SDHCカード、SDカード、SDXCカード | SDカード |
| 動画撮影サイズ | 1920 x 1080 (フルHD) | なし |
| 防塵・防滴 | ○ | なし |
| 幅 x 高さ x 奥行き (突起部含まず) |
約128.5 x 96.5 x 71.5 mm | 約125 x 92.5 x 67 mm |
| 質量(重さ) | 約650g(専用電池、SDカード付き) 約590g(本体のみ) |
約470g(本体のみ) |
| 発売日 | 2012年6月29日 | 2006年2月28日 |
| さて、*istDL2との性能差は、6年の歳月を考えると無理もない話ですが、画素数、記録サイズ、感度、液晶モニタ及びファインダー視野率の拡大、防水・防塵機能や動画撮影機能の追加などが挙げられます。 |
 |
 |
| 撮影画質ですが、左がK-30、右が*istDL2です。 レンズが違うので、風合いが異なりますが、まずはサイズ変更のみで比べてみてください。 これでは、差異はわかりませんね。 |
|
 |
 |
| 同じ部分を拡大してみると、ご覧のとおり。 *istDL2も結構健闘していますが、4倍位の精細さがあるはずです。 |
|
 |
 |
| さて、*istDL2が苦手だったのが、電球色のホワイトバランス調整です。 ちょっと小洒落た店に入ると、もう画面はオートでは画像補正の効かない赤褐色の画像になってしまいましたが、さすがにかなり自然な仕上がりになっています。暗く白い画面のオートフォーカスは、さすがに完全ではありませんが、AFスピードと静音性、精度は格段に上がっています。 まだまだ本格的は操作で使っていませんが、これからどんどんいろいろなシーンでテストしていきたいと思います。 |
|