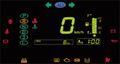 |
スパシオなぺーじ |
| 日本自動車博物館に行ってきました! |
 |
 |
| この夏の甲信越・北陸遠征の最終回は、石川県小松市にあります、「日本自動車博物館」のレポートです。 この自動車博物館の存在は知っていたのですが、場所が場所だけに行く機会もなく、今回もたまたま旅館の観光ガイドを見ていて思い出し、時間を作って強引に回ってきたものです。 山中温泉の花紫からは距離にして12キロ程度、時間にして20分程度の道のりです。花紫はチェックアウトが12時なので、早めに朝食を済ませ、家族が支度している間に駆け足で見てきました。 道中は、水田の中を走る快適なドライブコースです。 |
|
 |
 |
| このサイトでも、多くの自動車博物館を紹介していますが、長久手町の「トヨタ博物館」は展示台数約120台で、こちらのウリはほとんど動態保存であること。 「伊香保 おもちゃと人形 自動車博物館」は展示台数約70台で、ここでは「新車の状態で保存・展示」することといった印象があります。 そして日本自動車博物館は1978年(昭和53年)に富山県小矢部市にセメント販売業・石黒産業社長(当時)の前田彰三(初代館長)が個人収集した自動車をもとに開設。その後、1995年(平成7年)に現在地に移転し、開設した赤レンガ造り風の建物です。展示台数は約500台と、展示台数としては日本最大級で、高級車やスポーツカーよりも、国産の商用車や大型車、軍用車、共産圏の外車など、全国でもここしかないレアな展示車があることが特徴です。 個人収集なので、展示が雑多で、解説看板などが適当であったりする部分もありますが、同一車種や同一メーカーがまとまって年代ごとに並べられるなど、私のようなノスタルジーカーマニアにはたまらない内容になっています。もちろん、稼働状態の車両も多くあります。 |
|
| まずは屋外展示から |
 |
 |
| この3台は、東日本大震災発生後の支援物質の輸送、ガレキ搬出などのために、ダイムラーAG及び、その日本法人である三菱ふそうトラック・バス、メルセデス・ベンツ日本が日本財団に提供したした50台のうちの3台で、上左からゼトロス1833、ウニモグU5000、軍用ゲレンデヴァーレン 実はこの3台、軍用特殊車両仕様の展示車を日本国内仕様に最小限改造し、海外からかき集めて輸送したことから、日本国内の構造基準等法規に沿っていないものもであったのですが、政府と交渉し、2年間限定で国内使用許可を得て活動していたものです。その期間が切れて役割を終えましたが、後世に被災地での活躍の功績を残すことなどがあり、日本自動車博物館側で3台の車両を選択したものです。 |  |
 |
 |
| エントランス付近には、富山県警のC33ローレルベースのパトカー…といっても、これは劇用車の寄贈を受けたものと、セリカGT-FOUR A(ST-185H)です。 | |
| 三菱の街 |
 |
 |
| 三菱の街では、当時のフラッグシップでモデルチェンジのなかったことからシーラカンスと呼ばれていた「デボネア」を始め、各種ギャラン、ランサーなどがあります。 右は歴代小型車・軽自動車で、三菱360・500、ミニカ、コルトそして軽三輪のレオなどがあります。 |
|
| いすゞの街 |
 |
 |
| 次はいすゞの街です。 現在は乗用車から撤退してしまったいすゞですが、昭和の時代は高級車、ラグジュアリー、スポーツ、そして国内初のGTカーなど、高性能で個性的な名車を多数生み出していました。 写真は子供のころにうちにあったベレットシリーズ。高性能でしたが、キャブのご機嫌が悪いと、とにかくエンジンの掛からなかった思い出が残っています。 |
|
 |
 |
| 個性的な車造りのいすゞを代表する車種となるのが、117クーペ、ジェミニ、ピアッツァです。 ジウジアローデザインに高性能エンジンを搭載し、ラグジュアリーカーの先駆となりました。発売から10年間一台の廃車を出さなかったという記録は、未だに破られていないとのこと。 ジェミニ、ピアッツァはその後を継ぎ、ビッグホーンなどのSUVと並んで、いすゞの乗用車黄金期を飾りました。 |
|
 |
 |
| いすゞ乗用車のパイオニアはヒルマンミンクスをベースに完全自社製として生み出されたのが、左のベレルです。ベレルはクラウンやセドリックなどと並ぶ中型高級路線で売りに出ました。また、実用ディーゼル乗用車の先駆となりました。 右はその後を継いだフローリアン。私のイメージでは当時のフラッグシップでしたが、コンセプトとしてはコロナやブルーバードと並ぶ中型大衆車として設計されました。こちらも、ディーゼルエンジン音を響かせながら走っていた記憶が残っています。 |
|
| スバルの街 |
 |
 |
| スバルと言えば360ですが、バンタイプ、サンバーなどの派生種、後継のR2やレックスなどがあります。 普通車では、4WD乗用車の先駆であるスバル1000から初期型レオーネ、スイングバックなどがあります。 スイングバックは、免許取ったら欲しいと思っていた車の一つでした。 |
 |
 |
 |
| スバルスペシャリティーカーとして、故大藪春彦氏が絶賛していたアルシオーネとSVX。 そして右は、第28回東京モーターショー参考出品のキャスピター1989。「公道道路を走れるF-1」を目指し、ワコールと童夢との3社が共同で開発、エンジンは3.5Lの水平対向12気筒60バルブ585ps/10,750rpm、トルク 39,2Kg-m/10,500rpmを発揮。 |
|
| オート三輪の街 |
 |
 |
| 揃うと壮観な、オート三輪のコーナです。 ミゼット以外のマツダGB型やくろがねKP型など、貴重な車種が盛りだくさんです。 ちなみ、くろがねKP型は、以前紹介したとおり、うちの近所の運送屋さんに展示されています。 |
 |
| 日野の街 |
 |
 |
| ルノー4CVのライセンス生産で、国内パーツに置き換えた日野ルノー。 右はミケロッティデザインで流麗な貴婦人と呼ばれたコンテッサ1300。哺乳類的な顔をしていますが、エンジンをリヤに搭載しているので、後ろから見るとゴツいグリルで埋め尽くされていて、重厚感を感じます。 |
|
| マツダの街 |
 |
 |
| マツダ初の3ナンバーセダンで、現在まででもマツダ最大のプレステージカーであったロードペーサーAP。 マツダの軽量スポーツの一翼を担い、サーキットでも名をはせたサバンナ。 |
|
 |
 |
| 名車コスモスポーツの跡を継ぎ、ロータリースポーツにラグジュアリー路線を合わせ、バブルカーのはしりとなったコスモAP。 この博物館の順路で最初に出くわす、金箔張りに加賀友禅柄のカペラ。ちゃんと洗車に耐えるトップコートを施してあります。 |
|
| 四駆の街 |
 |
 |
| 私のハンドルネームにもなっている三菱ジープ。これはJ37の2代前のJ34・36。 右はその本家、ウイリスステーションワゴン475-44。作り物のような美しいボデーが質実剛健さを内包しています。 |
|
 |
 |
| 結構、デザイン的に好きな(というか、ランクル20系そっくりなのですが)通称北京ジープBJ-212。 反して、余りにも無骨、ウイリスジープを基にソビエトで製作された、通称イワンジープJAZ-69. |
|
 |
 |
| そして、元祖四駆とされているのがウイリスジープなのですが、実はこれはその民生用シビリアン(CJ)モデル。機能性や安全性が高められています。 右は、ジープほどハードでなくSUV的クロカン四駆のはしりとなったダイハツタフト。これの姉妹車として、トヨタからはブリザードという車種がありました。 |
|
 |
 |
| しかし、さすがのニッポン。実はジープにさかのぼること6年も前に、小型軍用四輪駆動車を製作していました。それがこの95式小型乗用車、通称くろがね四起です。 エンジンや車体形状など様々なタイプが4775台生産されました。 |
 |
 |
 |
| ランクルと双璧であった元祖四駆だったのが日産パトロール。よく消防車で見られたパトロールは、ランドローバーに似た60系ですが、これは極初期型の4W60型で、蝉のような顔と言われます。 右は民生用クロカン四駆の始祖となったスズキジムニーの水冷360版LJ-20。 |
|
 |
 |
| 最後に、ちょっと変わったところを。 左はドイツのキューベルワーゲンの流れを汲む軍用車で、のちに民生用も生産された、フォルクスワーゲンタイプ181。1.5~6Lのエンジンを積み、1983年まで製造されました。実はこの車は四駆ではなくRR。 そして、よく似たコンセプトなのが、右のいすゞユニキャブ。こちらは1974年まで製造されたFRクロカン。作業用というより、RVのはしりとなったものですが、余りにもスパルタンで、ちょっと先走り過ぎたかな?という感じです。四駆だったら買ってもよかったかなぁ。 ちなみに、となりの青い小型トラックは、トヨタRR16型。 |
|
| 軽自動車の街 |
 |
 |
| 軽自動車カテゴリーはまた別に展示されています。 商用車もない訳でなないのですが、この辺は伊香保に一歩ゆずります。 珍しいところでは、右の写真の一番左端にあるのが、日産自動車系列の自動車部品メーカー・愛知機械工業が、1962年から1970年まで製造販売していたコニー360です。 |
|
 |
 |
| ということで自動車創世記には、自動車車体メーカーや部品メーカーなどが独自に軽自動車を製造している時期がありました。 先ほどのコニー360を生産していた愛知機械工業で作っていたのが、左の写真手前からコニーグッピー、ヂャイアントコニー、そしてくろがねベビー、さらに右の写真が車体メーカーである住江製作所が製造したフライングフェザーです。 どれも、デザイン的には魅力的で、現在のミニカーに通ずるものがありますが、フライングフェザーに至ってはリヤカーのようなタイヤとフロントブレーキレスと、コストダウンの度を超えたところもあって、いくらなんでも買ってもらえなかったようです。 |
|
| ホンダの街 |
 |
 |
| ホンダの街に目新しいところはない…と思いきや、左の写真の手前から2台目の小形バンがL700です。キャッチコピーは「高速時代のライトバン」。特徴としてはS600用をベースに開発されたL700E型
687cc 水冷直4DOHCエンジン(52馬力、シングルキャブレター)や、フロントサスペンションに日本車初のストラット式を採用したことなど、当時として高度な技術を投入していた、T360トラックと同じ轍を踏んでいます(一説には、宗一郎氏が「レースで勝てないならトラックでも作ってろ!」ってハッパかけられて、DOHCをトラックに載せてみたとか。)。おかげで、あまりにも高回転型かつピーキーな性格のエンジン特性が嫌われ、わずか3年の短命で終わった珍車中の珍車です。 M魏の写真のバモスとステップバンは、昭和のホンダ名車ですが、その隅に隠れるように展示してあったのが、T360トラックのキャタピラ版。以降もホンダは、アクティトラックなどにもクロウラー仕様を準備しています。 |
|
| スズキの街 |
 |
|
| スズキの台数は少なくて、ここの他にカルタスとジムニーがあったくらいでした。 奥からスズライトキャリィ、フロンテ、そして小形車のフロンテ800などがありました。 |
| ダイハツの街 |
 |
 |
| ススキに比べて、ダイハツの街は充実しています。 ミゼットを始め、ハイゼットシリーズからフェロー、小型車としてコンパーノ、シャレード、そしてカローラと兄弟車のシャルマンがあります。 |
|
| 日産(ダットサン・プリンス)の街 |
 |
 |
| 日産系もダットサンとプリンスに分けて展示されているところがあります。 左はダットサンブランドの皆さん。 右はブルーバードの皆さん。こうやって見ると、個性的なデザインですね。特に4代目610系辺りが。 |
|
 |
 |
| プリンス系からは、始祖のプリンスセダンAISH-V。この丸っこいクルマがのちのスカイラインに発展していきます。 そしてのちに日産高級車の方翼となる、プリンスグロリア。セドリックとは違った威圧感があります。 |
|
 |
 |
| 一方のセドリックは、いくらか和のテイストを感じるのは、私だけでしょうか? | |
 |
 |
 |
 |
| そして、各形式のスカイラインも盛りだくさん。必ずしもトップグレードでないのがいい味出しています。 | |
| トヨタの街(トヨタウン?) |
 |
 |
 |
 |
| トヨタの街は特にコレクションとして目新しいところはありません。クラウンとコロナ一派の品ぞろえが圧巻ですが。 | |
| トラック、バス、消防車等の街 |
 |
 |
| ダットサンキャブライト1150とトヨエース(1t積)、トヨタスタウト(RK101)とトヨエース(PK32)。 スタウトは、まだ地方の消防団で現役の消防車があります。 |
|
 |
 |
| 軽ではないトヨタのミニエース(UP100)と日産ジュニア、ダットサン17Tと25T。似たような面構えですが、17年の年齢差があります。 | |
 |
 |
| セダン210の系譜をトラックに受け継いだダットサントラック220と223、ダットサンピックアップはセダンとトラックのいいとこ取り、緑のトラックはオオタKC型。オオタはその後、くろがねの日本内燃機製造に吸収されてしまいました。 | |
 |
 |
| 昭和の時代には結構よく見たのが、個人商店のダブルキャブの小型トラックです。 左はダットラの愛称で親しまれたダットサントラックダブルピックアップ、右はちょっとマイナーだったトヨペットコロナマークⅡピックアップ。 個人商店では、営業ユースとパーソナルユースを兼ねて、この手の車を所有する方がバンより多かったようです。私も隣のおじさん(米屋)によく駅まで乗っけてってもらいましたっけ。 |
|
 |
 |
| 大型トラックバスの街にはいすゞBXD30 ボンネットバス、トヨタDB100ボンネットバス、日産80型セミキャブバスなどが並びます。 また、消防車のコレクションも多く、右の写真は戦前の大蔵省印刷局に配備されていたダッジポンプ車。 |
|
 |
 |
| 戦後日本の日産中型トラックの代表作である580型のポンプ車版P580。フロントグリルがいかします。 他方、いすゞ中型トラックのベストセラーTX型。先ほどのBX型バスの兄弟ですが、グリルの仕様がちょっとこちらの方が繊細です。 うちは家業がダンプ屋だったので、TX型やキャブオーバー10tタイプTMK型などがマイカーでありました。 |
|
 |
 |
| この時代になると、絶対的にアメリカントラックの性能が勝っていた時代で、国産車は技術をまねながら成長していた時代でした。 左はフォードF8型シャシーに国内で艤装したポンプ車、右はトヨタGB型をベースにしたポンプ車。トヨタGB型はエンジン回りがシボレーの特徴を、駆動系やシャシーはフォードの特徴を捉えているとのことです。 |
|
 |
 |
| 意外かもしれませんが、昭和の初期は日本軍もフォードやシボレーなどのアメリカ製トラックを主力として使っていました。 左はシボレートラックですが、トラックの国産化を図っていた陸軍が民生用のトラックをベースに開発に着手、東京自動車工業(現いすゞ)の物がベースとなり、94式6輪自動貨車が誕生しました。性能的には十分でしたが、耐久性については試験を重ね改良を続けていたそうです。 シボレー製に比べると、グリルあたりに和のテイストが感じられますね。 |
|
 |
 |
| 時代が前後しますが、左は警察予備隊に供与されていたダッジウエポンキャリアの後継としてトヨタが製作したFQ型。自衛隊的には3/4tトラックと呼ばれるものですが、他にも日産製といすゞ製がありました。 右は満州事変時代に使われていたフォードトラック。氷点下30度の冬の満州では、一発でエンジンがかかるのはフォードトラックだけで、国産は夜通し練炭コンロで予熱していてもダメだったそうです。 |
|
 |
 |
| クラウンの耐久性を向上させ、タクシーや営業用として作られた姉妹車がトヨペットマスターですが、あまりにクラウンの出来が良すぎてタクシー会社もこちらではなくクラウンを使用することになり、余ったシャシーで作ったバンと小型トラックとされるのがマスターラインです。 後にクラウンベースのバンとなり、高級ステーションワゴンのはしりとなり、ビジネスユースだけでなく、ファミリーユースとしても一定の支持を集めました。 右はありがちのサンバーベースの可搬ポンプ積載車です。実は私、デラックストミカを持っているのですが、ちょっとこの車は艤装が違って、最後部のリヤエンジンの上にホースラックを挟んで補助座席が付いており、ポンプを積んでも足元に余裕があります。トミカのやつはエンジン上は全てホースラックで、座席は同じ高さでその前に取り付けられており、さぞ可搬ポンプで足元は狭かったことでしょう。 |
|
| その他の展示車 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 最後にミュージアムショップがあります。オリジナルグッズは少ないですが、ミニカーの種類は充実しています(レアものはなかったです)。 | |
| おまけ |
 |
 |
| 住において、動の空間が車だとすると、静の空間の代表がトイレであるということで、世界のトイレ(というか小便器)が展示…ではなく、動態保存で使用できます。 奇抜なものはありませんが、個性的ではあります。 |
|