
 |
キューブなぺーじ |
 |
4日目(最終日) 宇和島−四万十川−中村−宿毛−宇和−内子−松山 |
 |
 |
|
いよいよこの旅行も最終日となりました。なんとか3日間持った天気もとうとう崩れ、生憎の雨。しかしそれに負けじと、この日は国道320号、381号を経て、441号を四万十川沿いに遡ろうと思います。 初日にも言いましたが、四国の道は決して悪くはないのですが、ちょっと山間部に入ると途端に国道も1.2車線位になってしまいます。国道381号や441号は高知県西部と松山方面を繋ぐ幹線道路ですが、高速道路がまだ延びていないこの辺りにはまだまだ大型車も多く通ります。しかも川沿いには採石場が多くあり、度々10tダンプとのすれ違いを余儀なくされます。この日は月曜日でしたので一層交通量は多かったですが、走りなれた通勤ドライバーが多かったのでまだすれ違いは気を使わないで済みました。 写真のような道をみると、軽自動車がこの辺に多い(特にジムニーやパジェロミニ)のは納得できます。 |

|
最後の清流・四万十川 |
 |
 |
 |
 |
|
四万十川には清流というイメージがありますが、それ以外にも他の日本の川にない姿があります。それはこの緩やかな流れと広い川幅が、山間部を流れる部分から続いている風景です。急峻な流れと思われている四万十川はこの姿の方が代表的です。 しかし、山間部から一気に河口まで流れていくのには変わりなく、上流部にダムを持たない四万十川は急激に水量が増えることを広い川幅は物語っているのです。そこで必要なのが「沈下橋」です。 沈下橋は細い橋脚と薄い橋桁、そして欄干のない形状になっています。これは増水時に水中に沈み、流木などから破損を防ぐのが目的です。また、広い川幅で桁を高くすると、一層長い橋が必要になるので、高さを抑えた沈下橋で長さを稼ぐ目的もあります。 こちらは中村市に入ってすぐの「勝間沈下橋」です。 |
 |
 |
| こちらはそこから2つ下流の「佐田沈下橋」。ちょっと幅があって途中に待避所もあり、普通車ならすれ違いが可能ですが、橋の見通しがよく、それほど交通量がないので、みんな対岸で待ってくれます。 | |
 |
 |
|
四万十川はほとんど川幅を変えず河口まで流れています。結構上流まで船が上がっていくところを見ると、河口部は深さもそれなりにあるようです。 さて、旅行に行くとお土産やサンだけでなく、地元の一般商店やスーパーなどへ行くとお土産やサンにない地元アイテムを安く手に入れることができます。そこで今回も地元ショッピングセンター・デイズに立寄り、いろいろな商品を購入しました。 |
|
 |
 |
|
さて、四万十川まで来て食べたくなるのは「うなぎ」。先ほどのスーパーにもうなぎがありましたが、さすが地元はきちんと「地元養殖」とか「中国産」とか大きく書いて販売しています。 今回立寄ったのは津島町の国道56号線沿いにある「田むら」さん。特にどうということはありませんが、天然や四万十産でなくても地元ならマズイモノは出さないだろうとうな重を注文しました。ご存知の通り東京のうなぎは「背開き」ですが当然ここでは「腹開き」。いつもの調子で尻尾側からかぶりついたら...こちらでは尻尾落とさないようで、すごい骨が...... タレは蜂蜜味の甘〜〜〜いもので、しかも"つゆだく"。う〜ん?? |
|
 |
ちょっとみつけた気合入り初期型キューブと記念撮影。 とても同系車とは思えない変貌振り... |

|
古き学問と文明の町 宇和 |

|
 |
|
さて、昼食を済ませ松山方向に戻りますが、途中で立寄ったのがまず宇和町。宇和文化の里として町並みた建物の保存を行っており、大洲のところでお話した「えひめ町並博」の会場の1つです。 宇和の町並みは、江戸時代の宇和島街道宿場町と発展したところが中心になっています。この中には200年の歴史を持ち、各時代の有名人が泊まった旅館「松屋旅館」などがあります。 |
|

|
宇和町の中心的歴史建造物といえば「開明学校」です。明治15年に建築された建物で、すぐ隣には明治2年に建てられた開明学校最初の校舎である「申義堂」があります。
|
 |
歴史上の人物としてこの町に係わっていたのが高野長英。シーボルトの下で医学・蘭学を学んだ長英が蛮社の獄で捕らえられた後、火災に乗じて脱獄し隠れ住んだところの1つがここです。 ちっちゃな小屋のように見えますが、実は現在は2階建ての2階部分しか残っていないとのことです。 |
 |
古い建物の改修工事。どのような建物だったのか?どのような建物になっていくのでしょうか?? |

|
歴史と生活・文化が今だ息づく町 内子 |

|
 |
|
大洲を過ぎ、さらに松山方向に進むと内子町に着きます 内子は元々和紙や木蝋作りで栄えた商家の町並みが広い範囲に綺麗に保存され、多く残っています。内子の町並みがすごいのは、あたかもテーマパークのように整備されながら、実際に人が暮らす町の機能が維持されているということです。ということも合ってか、平日というのに多くの住民及び観光客がここを訪れており、活気があります。 右の写真は「木蝋資料館」。明治中期に建てられた本芳我家分家の屋敷土蔵です。 |
|

|
 |
|
少し町並みから離れたところにある「旭館」、明治14年に建てられた常設活動写真館です。 その後電気館と改名し、昭和40年代まで使われていたそうですが、現在は特に整備もされず、かなり荒れてしまっているのは残念なところです。 中をのぞいてみると古い雑誌かポスターの切り抜きが残っており、間違いなく映画館だった名残を示しております。 |
|
 |
内子の代表的な建物の1つが大正5年に建てられた芝居小屋「内子座」です。
過去に映画館や商工会議所、さらには解体の危機など数奇な運命を辿りましたが、昭和60年の修理・復元で現在は本格歌舞伎舞台から松竹新喜劇まで行う多目的ホールとして活躍しています。(資料館として施設見学もできます)
|
 |
街角で見つけた、その名も「火防地蔵」。いつ頃からこの古い町並みを守ってきたのでしょうか? |
 |
 |
| 現在、町並みを火災から守っているのはコレ。消防車が入れないほど道路は極端に狭くはありませんが、大事な初期消火に活躍するのはやはり消火器と消火栓。ホース収納「樽」にはホース、管槍はもちろん消火栓鍵やスピンドルドライバーが一体となっており、迅速な対応が可能です。 | |
 |
公共施設にも、古い建物が使われています。まず右側は明治11年に建てられた児童館。元々小学校の一部であり、その後郵便局、信組、農協の事務所として活用され、昭和58年に現在の姿で児童館として蘇りました。 左の建物は昭和11年に建てられた図書館。元々は警察署で、留置場が書庫になっているとか... |

|
エピローグ |

|
 |
|
さていよいよこの旅行も終わりを迎えます。メーターを見ると、この4日間でトリップメーターは一回りし、1,278kmを走行しました。 なかなか愛着が沸いたキューブでしたが今日でお別れ。いい走りをありがとうございました。 さあ空路でスパシオの待つ東京へ戻ります。(まさか、買い換えたと思った人はいないよね?) 今回の旅行は、一応同期生会ということで旅行はおまけだったのですが、行ってみて、さらに調べてみて、かなり多くの見所を落としていたことに気が付きました。愛媛だけでもこんな調子だったんですから、まだまだ四国は広い! 2004年の町並博の時にもう一度行ってみようかなぁ... |
|

|
四日目の燃費=16.56km/l ちょうど10・15程度の数値で締めくくりました。 極端に燃費のいい車ではありませんでしたが、慣らしの距離しか走っていませんので、まだまだこれからしょうね。 |
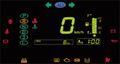 |
スパシオなぺーじ |


|
おまけ |

|
 |
|
子供向けには坊ちゃんグッズ。坊ちゃん列車のステーショナリー、プルプル電車やミニモデルなど。 どこでも見かけた「坊ちゃん団子」。餅や米粉の団子と思いきや、あんこ玉みたいな食べ物です。 |
|
 |
麺セット各種。一番右の「伯方の塩ラーメン」は前述のとおりです。塩味海苔が付いています。 その隣は石鎚山SAで見つけた「美川村の手作り・手延べそうめん」ソーメンフリークの私にとっては見逃せませんでした。 さらに隣は、有名店「ぶっかけの山下うどん」おみやげ版。レモンをかけるというのがポイントだそうで... 最後は、関東では買えない「金ちゃんラーメン」、デイズで買いました。袋麺にも数種の味、さらにカップタイプやてんぷらそばなどもありましたが、結構かさばるのでコレにしました。なかなか美味です。 |
 |
みかん物は結局買いませんでしたが、唯一のお土産がコレ、ポンジュースキャンディー。ポンジュースを売っている「えひめ飲料」ではなく、ドロップの佐久間製菓製でした。 |
 |
そしてこちらの銘菓といえばタルト。一六タルトや畑田の栗タルトなどがメジャーですが、大量に買っても食いきれないので、ちょっと毛色の変った物を選びました。 |