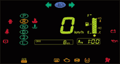 |
スパシオなぺーじ |
| 日本のガラパゴス 南島へ! |
 |
 |
| 「南島」は父島の南西に位置する、小笠原の中でも地形的にも景観的にも、生物学的にも貴重な島で、日本のガラパゴスとも言える島です。 そのような環境から、多数の観光客が訪れた事による外来種の持込や植生の荒廃、土壌の流出など、自然環境の悪化が進みましたが、現在その環境を戻すために ①11月上旬から2月上旬までの上陸禁止 ②最大上陸時間2時間まで ③1回の上陸は15名まで ④ツアーガイドの同行 等の規制が掛けられています。 ということで、11月の訪問時には行けなかったのですが、今回2月の訪問時にようやく訪問することができました。今回は二見港からピンクドルフィン号による、半日コースのホエールウオッチングと南島ツアーに参加しました。 |
 |
父島・二見港から南島までは直行で30分程ですが、この日は結構波も高く、また鯨を探しながらの航海で、父島の西岸を結構ゆっくり進みます。 これは父島の南西部に見られる「ハートロック」、恐らく石灰岩質の部分に割り込んだ火山性の堆積物が、赤いハート型を作り出しています。 |
 |
 |
| このシーズンはホエールウオッチングの時機なのですが、この日はかなり少なかったようです。それでもつがいのザトウクジラが結構見られました。 ザトウクジラはつがいで子供を育てるそうで、何度でもなかったですが、写真のようにペアのフルークアップも見ることができました。 |
|
 |
南島には島の南側から入ります。 もちろん桟橋などありませんので、ここから入り舳先を乗り移りやすい丈夫な岩場に押し付けて上陸します。ですから、ここに来る船は舳先に大きなクッションを付けています。 この入り江は「鮫池」と呼ばれ、ネムリブカという鮫の一種が棲んでいます。また、写真のように入り口が狭くて浅いので、潮を読み間違えると喫水の深い船は出られなくなるそうです。 当然、荒天の時は接岸できません。 |
 |
南島は石灰岩、つまり昔のサンゴ類の死骸が堆積してできた島が海中に没した「沈水カルスト」と呼ばれる珍しい地形です。ですから、写真のように荒々しい岩場が基本ですが、その上に堆積した赤土が表土を覆い少ない植生を維持しています。 右側の露出しているところは、植生荒廃で表土が流出したところで、その上側が回復した部分になります。 他にも植生回復を行っていたり、元々風化に弱く脆い石灰岩のところが多いことから、歩く道が決められており、それ以外のところに足を踏み出すことは許されません。 |
 |
南島、いや小笠原を代表する風景の写真です。 中央の風穴の手前は「扇池」と呼ばれる入り江で、石灰岩質の白い砂浜と、洞窟の向こうに見える青い海のコントラストは、作り物のような美しさです。 特に砂のきれいさは他に比類なきものです。 |
 |
白い砂浜から一杯顔を出しているのは、生きている貝ではなく、今から1,000~2千万年に絶滅した「ヒロベソカタマイマイ」の半化石です。 あまりにも生き生きしていて、とてもそんな前から埋まっていたとは思えませんが、ちょっと記念に持ち帰ることは厳禁です。 よく波に洗われて無くならないものだと思ったら、地層の中に奥深く堆積しているとか。 |

